今回取り上げるのは“フレイル”。聞いたことはあるでしょうか?
“フレイル”とは「Frailty=虚弱」を元に作られた造語のこと。
2014年日本老年医学会が提唱した概念であり、地域包括ケアシステム同様に高齢者社会に向けて普及を試みている言葉でもあります。地域包括ケアシステムについては過去記事を参照ください。
“Frailty”には「虚弱」と共に「衰弱や老衰」という和訳もあります。
「衰弱」「老衰」には、年齢を重ねることにより避けられない不可逆的なイメージがついてしまいます。早めに気づいて、対策をすれば虚弱状態から脱することのできる可能性は十分にあります。
そこで要介護状態に至る前段階、注意喚起を促す意味も込めて“フレイル”と呼ぶようになりました。
フレイルの要素は大きく3つ。
- 身体的側面
- 精神心理的側面
- 社会的側面
本記事を読めば、フレイルの仕組み、簡単なチェック方法、対策方法がわかります。
【東大考案!】まずはフレイルチェック!
東京大学高齢社会総合研究機構(IOG)の飯島勝矢教授らの研究チームが考案した簡易のフレイルチェックを紹介します。
「指輪っかテスト」
これは足の筋力の程度を診るテストです。
- 両手の親指と人差し指で輪っかを作る
- ふくらはぎの一番太いところを指で囲む
- 「囲めない」「ぴったり」「隙間がある」を診る
どうでしょうか?
「隙間がある」あなたは要注意。筋力不足です。
「ぴったり」なあなたも気をつけましょう。
「囲めない」あなたは、今後も筋力を落とさないように過ごしましょう。
「イレブンチェック」
11個の質問で「栄養状態」「運動面」「社会とのつながり」を確認することができます。
全て「はい」か「いいえ」の2択で答えます。
- 同年齢の同性と比較して、健康に気をつけた食事を心がけていますか?
- 野菜料理と主菜(肉または魚)を両方とも毎日2回以上は食べていますか?
- 「さきいか」「たくあん」くらいの固さの食品を普通にかみ切れますか?
- お茶や汁物でむせることがありますか?
- 1回30分以上の汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか?
- 日常生活において歩行または同程度の身体活動を1日のうちに1時間以上実施していますか?
- ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いと思いますか?
- 昨年と比べて外出の回数が減っていますか?
- 1日に1回以上は、誰かと一緒に食事をしますか?
- 活気にあふれていますか?
- 何よりまず、物忘れが気になりますか?
*質問4.8.11は「はい」、それ以外は「いいえ」が多いほどフレイル状態に近くなります。
こちらもどうでしょう?
✅友人と一緒に歩いていてもついていけない。
✅ペットボトルのフタを開けるのが大変。
✅ステイホーム、リモートワークで家から出られない。運動機会が減った。
こういった生活が長期間続くことでカラダは確実に弱っていきます。特に高齢者では転倒や持病の悪化などにより、寝たきりの要介護状態が近づいてしまいます。
フレイル3要素
冒頭でもありましたが、「身体的側面」「精神心理的側面」「社会的側面」があります。
「身体的側面」
筋力低下や関節痛、骨の変形などの影響によるものです。
動きが遅くなる。よくつまずく。なんだか疲れやすい。そんな状態がこの身体的側面に当たります。
「サルコペニア」「ロコモティブシンドローム」などが関連してることも多いですね。
サルコペニア=加齢や病気により筋肉量が減ること。
ロコモティブシンドローム=移動機能に低下がある状態(立つ、歩くなど)
固い食べ物が食べるのが億劫になった。肉類(タンパク質)を食べなくなった。なども当てはまります。身体的側面には栄養面も大きく影響があります。
「精神心理側面」
認知症やうつ状態など原因のもの。
どちらも生活への意欲が低下し、動くことをやめてしまいます。認知症の場合は、徘徊などの理由で動くことを意図的に制限されてしまうことも問題です。
足腰がいくらしっかりしていても、気持ちの面で動けなければいずれ筋肉もなくなってしまいます。
「社会的側面」
閉じこもりや役割の消失などが原因のもの。
社会的つながりが少なくなると、外に出る機会を失い、カラダは衰えてしまいます。
家の中での役割も重要です。仕事や趣味活動、掃除、料理、洗濯など。
特に男性は仕事1本で生きていると、退職した時に何もすることが無い。という状態になりやすいようです。若いうちから家の中での役割や趣味を持っていることが、フレイル予防にもなります。

フレイル状態のデメリットは大きい。
フレイルは要介護状態の1歩手前の状態。要介護では無いから大丈夫?
いえいえ、常にギリギリの状態と思ってください。
フレイル状態では、何らかのきっかけであっという間に要介護状態へ移行してしまいます。回復も遅く、寝たきり状態に陥ったり、死亡リスクが高いことも報告されています。

例えば、フレイルで無い人ならすぐに治る風邪でも、長引いてしまったり、感染症の併発をしたりなどがあります。同じ転倒でも骨折のリスクが高いなどデメリットは多いです。
精神的にもちょっとした環境の変化に耐えられず、塞ぎ込んでしまう人も少なく無いでしょう。
さらには困った時でも社会的つながりが乏しければ、助けてくれる人もいないという状況が待っています。
こんなマイナスだらけのフレイルですが、まだ前段階。
できることはいっぱいあるので、今日から1つずつ取り組んでいきましょう。
フレイル予防のポイント3つ
厚生労働省でも次の3つのポイントを進めています。
「栄養」「身体活動」「社会参加」
厚生労働省「食べて元気にフレイル予防」
栄養
朝・昼・夜の3食をしっかり食べることは基本です。
その中でもタンパク質を多く取ることを推奨しています。タンパク質の摂取目安としては、
体重1kg=タンパク質1g
といわれています。
タンパク質は肉類ら乳製品、豆製品に多く含まれています。
しかし毎日バランスよく取るのは難しいものなので、おすすめはプロテイン摂取ですね。
プロテインというと筋トレしている人のイメージはありますが、タンパク質不足が多い現代人にはサプリ感覚で飲むことがおすすめです。最近では、低糖質や美容成分の入った飲みやすいものもあります。
身体活動
動物である以上運動は必須です。
運動としては筋力トレーニングと有酸素運動の組み合わせがおすすめです。

運動、運動って、どんな運動をすればいいのかな〜
今まで運動機会が無い方は。有酸素運動として散歩から初めてみてはどうでしょうか?
よく1日1万歩と聞きますが、最初は1日5分程度からで良いと私は考えています。
運動で大事なのは継続することが重要です。毎日1万歩はいきなり始めるにはハードルが高いので、まずは5分からと決めてやっていくと継続しやすいですよ。
社会参加
心の健康もフレイル予防の重要な対策。
年齢を重ねると人間関係が鬱陶しくなり、シャットアウトしがち。さらには感染対策などで、人との付き合いがより遠くなっています。
そんな時はSNS等を積極的に使っていきたいですよね。お盆でもリモート帰省など、話題になりました。
どんなに歳を重ねても、これからの時代はオンラインが必須になると思うので使いこなしたいところです。
ただ私もまだ古い人間ですので、人と人のつながりはやはり、直接会うことにあると思います。直接対面して、相手の表情や匂い、声色などを感じ取り、大勢で笑い合うことはこれからも重要と考えています。
まとめ
フレイルは前段階だけど、常に要介護状態へのギリギリの状態。
怖い未来がすぐそこに迫っている状態ですが、ポジティブに捉えればまだ間に合う状態です。
自分自身もチェックももちろん大切ですが、周りの人たちの健康も気を使うことで健康な人を1人でも増やしていきたいですね。



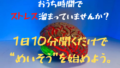
コメント