間取りや設備など徐々に進んできたある日、
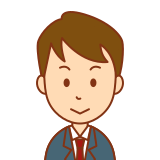
だいぶ煮詰まってきたので、そろそろ”設計”をいれましょう!!
設計士さんの登場です。設計士さんとは家の大きさや窓の位置、扉の位置、耐震性能の確認など営業さんと決めた間取りで、法律内で適しているかの確認作業です。
私の営業さんは”1級建築士”の資格を持っていました。設計士さんの名刺にも”1級建築士”と書いてありました。

設計士と建築士?何が違うんだろう??
家づくりにはあまり関係がないかもしれませんが、2つの違いを知らないと相手のプライドを気付けてしまうこともあるとか。
マイホームを建てる際には人との関係性はかなり重要です。気持ちよくマイホーム計画を進めていくには知っておいても損はないでしょう。
- この記事でわかること
- 設計士の仕事
- 建築士の種類と仕事
設計士という資格は無い
まず、設計士という資格はありません。
ちなみに建築士は1級や2級などがあり、国家資格になっています。
設計士はあくまで役割のことであり、ハウスメーカーや建築事務所などで主に設計業務に携わる人のことを指します。
つまり、特に資格がなくても設計士は名乗れます。
よく考えると”設計士”ってかなり広ーい意味を含んでいます。
建築物でなくても、飛行機や船などの機械類の設計でも”設計士”と呼んでいるはずですからね。
建築士の種類は大きく3種類
建築士の主な業務としては、
- 建築物の設計
- 工事管理
- 鑑定評価
- 行政手続きの代行
があります。
建築士の種類としては1級建築士、2級建築士、木造建築士があります。1級建築士のステップアップ資格としてあるのが、構造設計1級建築士と設備設計1級建築士。
建築物の規模によって対応できる資格が変わります。
1級建築士の場合
1級建築士は国土交通大臣が免許交付をしています。つまり権利を与えているのは国。
かなり強い権限があると言えます。1級建築士の資格があれば、学校や病院など大きな施設の設計も問題なく行えます。
国家試験の合格率は例年10%前後になっており、狭き門と言えますね。
この1級建築士を資格をもった設計さんであれば、「設計士さん」と呼ばれるのは不本意かもしれませんね。
なのでかはわかりませんが、私の営業さんはいつも「設計士の〇〇」では無く、「設計の〇〇」と呼んでいました。
2級建築士の場合
2級建築士の免許交付は都道府県知事から発行されます。
1級建築士と比べると、建築士法により建築できる基準が制限されています。
- 構造の種類:木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造
- 木造建築物の規模:高さ13mかつ軒の高さ9m以下、2.3階では延床面積1000㎡以下
- 木造以外の建築物:高さ13mかつ軒の高さ9m以下、延床面積30〜300㎡以下
- 他の建築物:延床面積1000㎡以下
色々とありますが、戸建住宅を建てるには1級でも2級でも問題ありません。
設計できる範囲はちょうど一般的な戸建住宅までとなっており、ケースによっては2級建築士の方が戸建専門の建築士と言っても過言では無いかもしれません。
2級建築士の国家試験合格率も20%前後と難しい試験と言えます。
木造建築士の場合
2級建築士と同様に都道府県知事から免許が発行されます。
名前の通り建築できる建物は木造に限られ、規模は2階まで、延床面積300㎡以下まで。
一般的な住宅は100㎡〜150㎡なので、ある程度の施設の建設まで行えます。
木造建築のスペシャリストなので、木への知識は豊富。
歴史的建造物の修復場面では、その専門性の高さから1.2級建築士よりも活躍が見込めます。
新築住宅においては、そんなに気にしなくても大丈夫
特に新築住宅の設計では、
- 建物の配置やデザイン
- 構造躯体(こうぞうくたい)
- 電気・空調の設備
上記3点をチェックしてもらいます。
1級、2級建築士の違いは建築できる規模の違いなので、新築住宅の設計には大きな影響はありません。
営業さんとの打ち合わせでは、希望を含めてのお家づくりを考える。
設計さんとは、より現実的なお家づくりの打ち合わせをすると言ったイメージです。
より良い家にするにはたくさんの人の意見を参考にする方が、気づきが多く得られます。念入りに確認作業することでトラブルや後悔することが減ると思いますので、営業さんとも設計さんとも仲良く打ち合わせをしましょう!

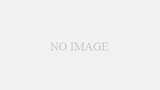

コメント